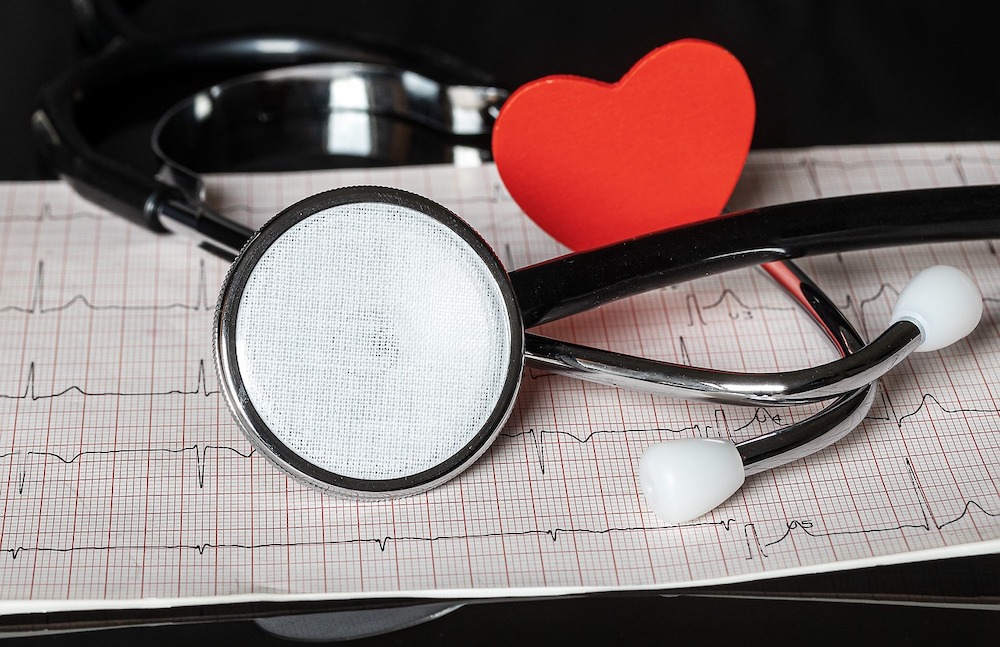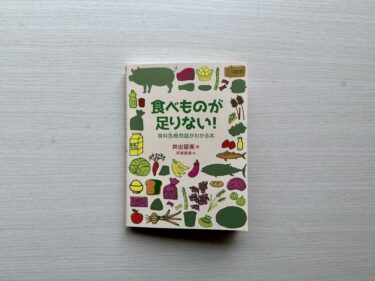牛の診療をするにあたって身体検査の精度を高めることは重要です。基礎中の基礎の部分ですが、定期的に復習しないといざというときに大事なポイントを見落としてしまいます。診療に慣れてきたときにこそ見直したいところです。
今回は、牛の身体検査の基本である「視診・触診・聴診」の仕方について紹介します。正常値を覚えておくのは当然として、異常値から何が分かるのか理解しておくのも大事です。基礎的なことですが、初心に戻って復習してみましょう。
牛の身体検査

牛の身体検査の流れは、視診・触診・聴診の順番で行うのが基本です。目で見て、手で触れて、音を聴く。外側から徐々に内側へと検査していくイメージですね。
視診
牛の視診では、下記の項目は必ずチェックしておきましょう。
- 活気・食欲
- 体型・毛艶
- 姿勢・歩様
- 光や音への反応
- 皮膚・肢蹄の状態
- 眼・耳・鼻・口の状態
- 胸部・腹部の動き方
- 筋肉の左右対称性
飼槽や尿溝に注目するのも大事なポイントです。
触診
触診で大切なのは、次の項目です。
- 体温測定
- 直腸検査
- 第一胃の触感
- 乳房の熱感・硬結感
- 尾力
- 腫脹部・疼痛部の熱感・波動感
- 臍の深部触診(子牛の場合必須)
温度・硬さ・弾力性・疼痛の有無などに注目しながら触診すると、何かしらのヒントが見つかります。
聴診
牛の聴診で重要なのは、下記の通りです。
- 心音
- 肺呼吸音
- 第一胃の収縮音
- 腸の蠕動音
聴診は、視診や触診と比べるとやや分かりにくいので、少し詳しく解説します。
心音
- 第Ⅰ音:心室の収縮開始と一致(収縮期心音)。房室弁の閉鎖によって生じる。
- 第Ⅱ音:心臓の拡張開始と一致(拡張期心音)。半月弁(大動脈弁、肺動脈弁)の閉鎖によって生じる。
- 第Ⅲ音:通常は聴取できない。心房から心室への血液流入が減速するときの音。
- 第Ⅳ音:通常は聴取できない。心室に血液が充満し、心室が拡張するときの音。
高血圧の牛では、第Ⅰ音が分裂して聞こえることもあります。
ギャロップ(三部調)とは、第Ⅲ音または第Ⅳ音が異常に強勢になった場合に聴かれる音です。
- 肺動脈弁:左側第2-3肋間、肩関節よりやや低め
- 大動脈弁:左側第3-4肋間、肩関節の高さ
- 左房室弁(僧帽弁):左側第4-5肋間、肩関節よりやや高め
- 右房室弁(三尖弁):右側第4肋間、肩関節の高さ
心内膜炎や心奇形の牛では、異常箇所で心雑音が聴こえる場合が多いです。
肺呼吸音
●肺呼吸音の増強
肺炎、気管支炎、喉頭炎、気道の狭窄などにより肺呼吸音が増大します。
●肺呼吸音の減弱
肥満の牛では、肺呼吸音が聴こえにくくなる場合も多いです。
肺組織に炎症・水腫・膿瘍といった病変があると、その箇所は無気肺部分となるため、肺呼吸音が聴こえなくなります。
●異常音
- 湿性ラッセル音:気管支内の分泌物が呼吸によってかき乱されて生じる音。断続性ラ音、水泡音、捻髪音とも。
- 乾性ラッセル音:気管支内の異物が呼吸によって振動するときに生じる音。連続性ラ音、笛様音、鼾様音とも。
肺水腫・肺出血では湿性ラッセル音が、化膿性炎肺炎・クルップ性肺炎では乾性ラッセル音が聴こえる場合が多いです。
第一胃の収縮音
第一胃の収縮音を聴くときは、左けん部で2分間を目安に聴診しましょう。正常な牛では、1分間に1〜2回の強い収縮音が聴こえます。
腸の蠕動音
腸の蠕動音は、右側腹部で聴診します。便秘・腸閉塞・腸管変位の牛では、蠕動音が減弱している場合がほとんどです。
身体検査の正常値一覧
| 成牛 | 子牛 | |
|---|---|---|
| 体温 (℃) |
38.0〜39.0 | 38.5〜39.5 |
| 心拍数 (回/分) |
64〜80 | 80〜120 |
| 呼吸数 (回/分) |
20〜30 | 24〜36 |
文献によりデータにばらつきはあるものの、実際の臨床現場では上記の範囲内であれば正常値と判断していました。
異常値から分かること

体温・心拍数・呼吸数の増減によって、ある程度は病態を把握することができます。
体温の異常
- 高体温:感染症、炎症性疾患、腫瘍性疾患、熱中症など
- 低体温:低Ca血症、大腸菌性甚急性乳房炎、大量出血など
出生直後の子牛で肺の機能が未熟だと、他の子牛と比べて低体温になる傾向があります。
心拍数の異常
- 頻脈:成牛では90回/分以上、若牛では100回/分以上、子牛では130回/分以上が頻脈の目安
- 徐脈:迷走神経の緊張、房室ブロック、低血糖などが主な原因
「心拍数>脈拍数」の場合は、心房細動となっている可能性が考えられます。
牛の脈拍数は、直腸検査により外腸骨下動脈に触れることで測定可能です。
呼吸数の異常
呼吸困難の牛では、肺呼吸数が増加します。胸部の肺呼吸音が聴こえない場合は、気管付近で聴診すると分かりやすいです。
牛の右肺前葉前部には「気管の気管支」が存在し、肺炎のリスクが最も高い場所となっています。体格の大きい成牛では肺呼吸音が聴こえにくい場合も多いため、肺炎を疑うときは右肺前葉の音をよく聴いてみるといいかもしれません。
まとめ
牛の身体検査は、視診・触診・聴診という流れで進めていくのが一般的です。言葉が通じない牛の状態を把握するためには、確かな知識にもとづいた鋭い観察力が求められます。
特に聴診は、牛の体の構造をよく理解したうえで行わなければなりません。回数や雑音などにも注目しながら、牛の状態を正確に見極めましょう。